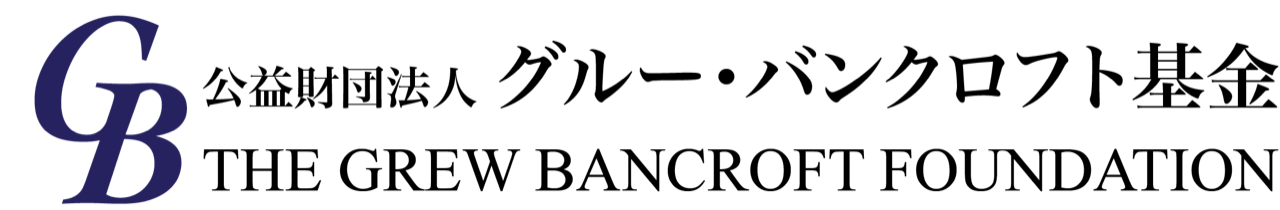基金の目指すもの
基金概要
グルー・バンクロフト基金は、日米相互理解の推進に尽力した戦前の二人の駐日米国大使の名を冠し、日本の高校卒業生の米国留学を支援することを通して、日本と米国の良好な関係を維持推進するとともに国際社会で有益かつ指導的な役割を果たす人材を育成することを目的とする公益財団法人です。1928年の創設からこれまでに約200名の基金奨学生が40を超える米国の四年制大学を卒業し、民間企業、政府機関、国際機構、大学・研究所、メディア、市民社会団体等の多様な場で活躍してきました。今でも基金は毎年10名前後の奨学生を米国に送り出しています。その一人一人が充実した大学生活を送り、将来の夢を育み、生涯の友を得、卒業して世界に飛び立っていくこと、基金はそれをしっかり見守っていきます。
女性リーダーを支援する「捨松スカラシップ」
⼥性の社会的地位向上を⽬指す⼥性リーダーを育て⽀援するための奨学⾦です。⼤⼭捨松は、明治政府から⽇本初の⼥⼦留学⽣として⽶国に派遣され、1882年に Vassar College を卒業し帰国。以来、⼥性の社会参画に⽴ちはだかる⽇本社会の厚い壁にチャレンジしながら⽣涯を終えました。
それから約⼀世紀半、⾃らも捨松と同じようなジェンダーギャップを体験した捨松の曽孫 久野明⼦⽒(基⾦評議員)は、次世代の⼥性リーダーを育てていく必要を強く感じており、新しい奨学⾦設⽴をグルー・バンクロフト基⾦に提案しました。2025年現在、一期生をWellesley Collegeに、二期生をMount Holyoke Collegeに派遣しています。
派遣先大学の特徴
グルー・バンクロフト基金では、奨学生を米国の著名な小規模・全寮制のリベラルアーツ大学に送ります。これらの大学は通常大学院を持たず、学生数が1学年500人前後と小規模で、学生は教えることに熱心な教授陣から少人数のクラスで探究型の密度の濃い授業を受けることができます。
教育内容については、文系・理系の枠を超えた幅広い知識の習得や現実社会に関する問題意識の醸成を迫る一方で、個々の学生が自らの興味・関心に基づいて学びを極められるようダブル・メジャー、内外他大学での期限学習、企業インターン等多様な選択可能性も組み込まれています。
また、学生はほとんどがキャンパス内の寮で生活を共にしながら、それぞれの自己実現に向けて切磋琢磨します。個の教育を重視する米国のリベラルアーツ大学では留学生も含めて全ての学生に教員アドバイザーがつくほか、生活面でのガイダンス制度も充実しています。
グルー・バンクロフト基金の奨学生は、同じ大学に在学中の先輩学生や卒業生に相談することもできます。また基金奨学生同士のSNSグループがあるほか、基金理事が定期的に派遣先大学のキャンパスを訪問し、食事会や個別面談を行っています。
代表理事メッセージ
 前田正吾(Wesleyan University 1979年卒業)
前田正吾(Wesleyan University 1979年卒業)テスト結果は受験者のことを何も語らないとして、50年以上も前から学力テストは入試に必要なしとしている大学がアメリカにあります。この考えに大いに共感を覚えました。振り返って、奨学生選抜では何をもって判断するのか、国際社会にとってどのような人材が求められるのかを改めて考えてみる必要があります。
社会にとって重要な要素として多様性があると思います。日本では多様性を受け入れ促進しようと心から思っている人は少数派ではないでしょうか。しかし多様性のある社会は活力が生まれイノベーションにもつながるのではないでしょうか。他人とは違う考えを持ち行動する勇気、常識にとらわれない思考力、そのようなものを持っている若者を選抜し、4年間の米国リベラルアーツ大学留学の経験を通して大きく成長するのを奨学金事業を通じて今後も支援してまいります。
1943年、太平洋戦争の真っただ中に、一人の青年がニューヨークから2ヶ月を超す長旅を経て横浜港に到着しました。当基金の奨学生で日米開戦後、在籍していた大学学長による身分保証を受け、当基金のアメリカ人関係者の支援により卒業まで勉学を無事に継続することができたのです。当時の当基金の報告書には送金ができず音信不通とありました。
当基金はこのような厳しい状況を乗り越えて2028年には設立100周年の節目を迎えます。多くの皆様のご支援とご指導に心より御礼申し上げるとともにこれからも一層の努力を惜しまない所存です。皆様の更なるご指導、ご支援を心よりお願い申し上げます。
日米関係がこれからも紆余曲折があったとしても両国にとって極めて重要であることは変わりありません。当基金の奨学生が多岐にわたる分野で日米の相互理解に貢献し、日本の社会そして国際社会に有益な活動をすることを願っております。